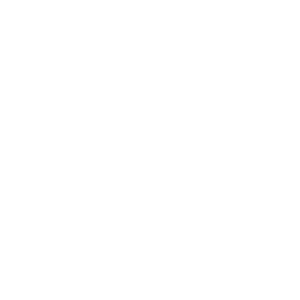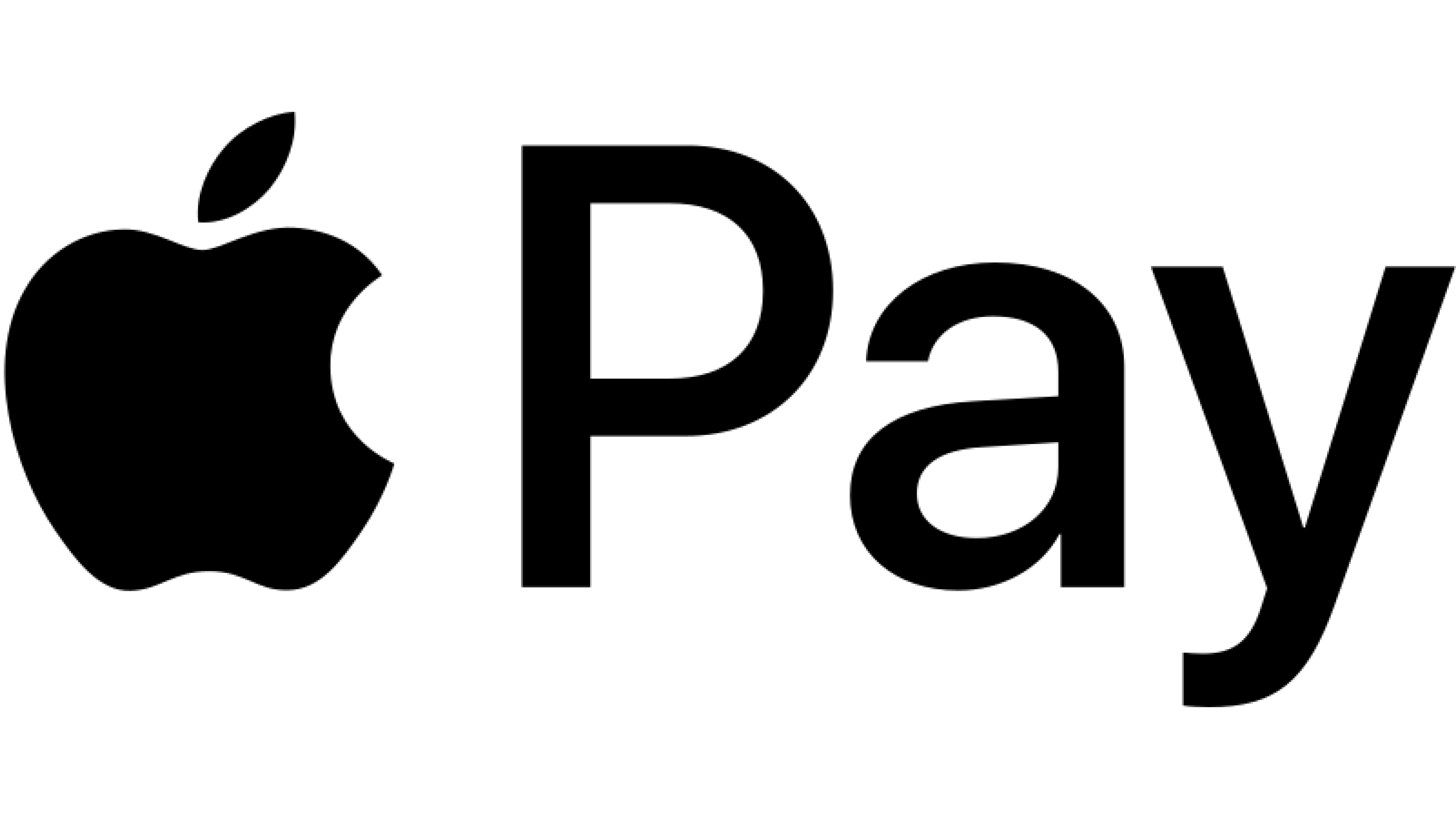本サイトに掲載されているコンテンツは、著作権法および関連する権利に関する法令を遵守しています。権利者の許可なく、著作物を複製、転用、販売、翻案、頒布、転載、貸与、公演等といった二次利用をすることを固く禁じます。ここに定められた義務の違反行為を発見した場合は、ただちに告発されます。
パンデミック時代の愛
六月一六日金曜日、夕方六時。地下鉄の車内は混雑していたりしていなかったり。暑くて、乗客は神経を高ぶらせ、とにかく家に帰りたいと思っている。君たちふたりは近いけれど、近すぎない場所に立っていて、一瞬、お互いの手が手すりの上で偶然に触れ合う。君はすぐに手をどかし、謝り、その短い謝罪の言葉が本気であることを示さなければならない。「気にしないで」とその人は、ちらっと見て言う。それ以上のことは起きない。それでも君は、マスクで半分隠れた顔から見えるビロードのような視線、手首、髪、爪にまで目を留め、「よくあることだよ」と言いたげに残ったままの、寛容ながらも自意識過剰な微笑みに気づく––––それは、君や他の乗客に向けられているのではなく、消えるはずなのに消えない気まぐれな後知恵のようにさまよっている。君はその笑顔を見たいと思う––––マスクを外して。そして、気づけば首のあたりのぼんやりとした肌の光沢を眺めていて、かなり日焼けしているけれど、どうやって、誰と、どこでそうなったのかと思いを巡らせる。訊いてみたくてたまらなくなるが、その言葉すら思い浮かばない。とぎれとぎれの君の視線は、(勘違いでないことを願うが)何かを打ち明けるような、皮肉な眼差しを生む––––君の警戒心は、これは全部頭のなかのできごとで、実際には起きていないし、起きていたとしても、ただ同じ車両に乗り合わせただけの、早く帰宅してマスクを外し、シャワーを浴びてから、友人とディナーを一緒にしたいと思っていて、月曜日の朝まで地下鉄のことなど考えもしないふたりの見知らぬ者同士の間で生まれたばつの悪い瞬間というだけと言ってくる。昔の知恵は正しいという声が聞こえてきそうだ––––地下鉄で起きたことは、そこだけのこと。
地下鉄は何かが起きるような場所ではないし、見知らぬ人たちは、誰かを引き止めもしなければ、誰かに引き止められもしないとわかっている。じっと何かを見ていると、すぐにいかがわしいと思われてしまうが、その人が誰なのかもわからない。それでも君は、何かユーモラスなこと、あるいは少し大胆なことが言えたらいいのにと思う。何かがおかしいとか、恥ずかしいとか、近くに立っている人に聞こえてしまうとか、あるいは、すぐにもっと良い瞬間が訪れるかもしれないし、良い瞬間というものはいつだってまた訪れるものだ、などと考えて、こんなふうな瞬間を何度逃してきたことか––––だから君は期待する。人生とは、今ここで起きていることだと言う人もいるけれど、人生は「次はもっと良くなる」の連続にほかならない。だから、君は台詞の練習をする。「君はいつもこんなふうに知らない人を見つめるの?」という質問には、「いや、一度もないよ。でももう二度と会わないかも知れないから、見つめてしまったんだ」あるいは、どの駅で降りるのか尋ねられたら、「二駅前さ」と気の利いた答えを返す。「そうしたら、どうして電車にまだ乗ってるの?」「そう君が訊くのは、すでに答えがわかっているからだろう」
君は何かしゃれたことを言おうとする。 でも、何も出てこない。
ぶざまになってもいいから、ちょっとした言葉を投げかけたいと思う。でも、それさえ見つからない。
何か思いつく?
だめだね。
みんなに見られているように感じるからだろうか。 あるいは、君が発する言葉が、非難の嵐を呼ぶかもしれないからか。それか、これまでずっとつきまとってきた、あの紛れもない「No」が怖いのかも知れない。人生の「Yes」はいつも消えるけれど、「No」はいつまでもずっと残るから。
でも君は、何も考えずに 「君にマスクを外してと頼むのは、完全に間違っている?」と尋ねる。
「どうして?」
「君の顔を覚えておきたいから」
「どうして?」
「何かが起きているのに、それが何なのかその名を知るのが怖いんだよ」
マスクが静かに下げられる。
「これでいい?」
「ああ、本当にありがとう」
しかし、今度は思いがけないことが起こる。誰かに訊かれるなんて思いもしないので、百万ドル賭けてもいいとすら思ったことが。
「さあ次は君の番だ」
「僕の番?」
「マスクを外すんだよ」
僕たちは大笑いした
「何かが起きているって信じる?」
「たぶん……わからないけど。君はどこで降りるの?」
「二駅前さ」